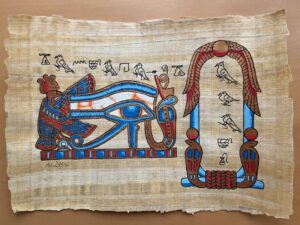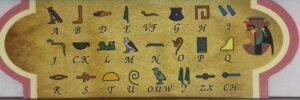2024.6.11 運転止める?続ける?
眼科の学会も規模の大きなものから小さいものまで。
森(眼科全体)に対してか、木(病気から・症状から・検査から・治療から…など)に対しての学会か。
今回は視野画像学会。
以前は視野学会だったのですが、眼科の画像機器の進化は著しく、視野画像学会と名称が変わりました。
開催地は新潟。
2回目の新潟です。
初めての新潟は、研修医一年目、初めて学会参加でした。
初学会参加に緊張と興奮。
でも、講演内容はほとんど理解出ず。
同期と『よくわからなかったね~』(研修医あるある)
上司I先生(女性)が登壇されたのを『かっこいい~すごい~』と眺めていただけ。
あっと言う間に学会が終わり即帰路に。
何が何だか?学会って異次元?
さて2回目の新潟は…
今回聞きたかったセッション、座長はI先生。
あの頃30代で登壇されたのですが、今もずっとパワフルでお元気、緑内障や視野の世界では重鎮です。
テーマは『視野と運転』
日本視野学会には「交通と視野委員会」があり、運転免許と視野についても調査研究が行われています。
現在、免許更新には規定の「視力」は必要ですが、視力が適すれば視野異常については触れていません。
しかし診察していると、視力が出ていても視野欠損・視野狭窄の患者さんは多くいます。
高齢者の運転が問題になっています。
運転は、認知・判断・操作からなります。
認知の中には視野障害も含まれています。
信号が見にくい・夜間見にくい・雨天に見にくいなどは、加齢に伴い自覚が増えますが、それでも高齢者で自覚しているのは4割と報告されています。
視野異常がある場合も同様で、自覚のない人が多いです。
高齢&視野障害ありは要注意です。
視線(眼球運動)のばらつきは、視野の広がりと連動しています。
視線のばらつきが小さいと事故を起こしやすく、大きいと事故を起こしにくいとされています。
視線のばらつきが小さいということは、注意力が低下しているということです。
高齢者では小さくなり、若い人では大きい傾向があります。
DS(ドライビングシュミレーター(模造運転装置))では、年齢が上がるにつれ、視線の水平方向のばらつきが小さくなったと報告されています。
速度によっても、視野の動きは小さくなります(より速度が上がると視野が狭くなる)。
またDS上で緑内障患者さんを対象に検証したところ、交通事故(仮想)の直前の視線の動きは小さくなり、さらに垂直方向の低下が著しいことがわかりました。
上方で信号を見、前方水平上に車や人を見、下方で計器を見ることを絶えず繰り返して運転しているのですが、どこかで少し視線が停留した時に事故が起こっています。
注意が向く箇所が多いということは、視線が大きいということ。
DSの目的は、自分の運転を模擬体験し、どこにリスクがあるかを自覚してもらうことです。
自身の視野異常を理解し、眼科医の助言の元に、注意して運転することで事故を起こさないようにする。
もしくは、視野異常を理解した上で、運転を止める自己決断をする。
DSおよび運転外来は、全国で2施設しかありませんが、私たち眼科医も運転が気になる患者さんには助言をしています。
2シーターのマニュアル車を運転していた(若かりし頃)院長も、運転技術の低下・視線のばらつき低下を感じるこの頃。
運転は最低限に。
公共交通機関&ママチャリ大いに活用しています。
運転が気になると思う方は、ご相談ください。