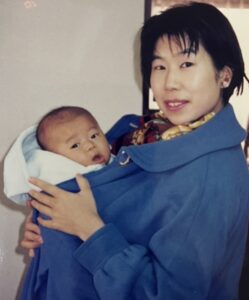2026.1.6 未来を明るく
昨年大晦日に無事篠座神社の眼御守が届きました(ほっ)。
手紙とともに。
『中略~大神様の尊い御神徳がかがふりますようご祈念申し上げ、右、取り急ぎお届けのご挨拶といたします。』(原文ママ)
今年一番の御守は篠座神社の眼御守。
クリニックの診療だけでなく往診もする院長は、常々老後の生活のことも考えてしまいます。
往診は、老後についても転ばぬ杖を学ぶ場でもあります。
『テレビが見にくい』往診先での訴え。
眼鏡で調整できそうです。
『眼鏡を処方しましょうか?』
『でも、たくさんあるからいらない』
テレビは小型サイズ。
テレビの位置を前にするか、椅子を前に持っていくかの提案に『でも、ここから見たい』
眼科医、力及ばず(というか説得できず)『もう少し様子見ましょうか…』としか。
別の個人宅では、ベッドで基本生活されていますが、大画面のテレビが設置されておりニュースや娯楽を楽しみにしておられました。
そんないきさつで、院長も自宅テレビを新調。
以前のもそこそこの大きさでしたが、思いっきり大画面に。
テレビの視聴時間は1日30分弱でしたが、大画面になったことで今までスマホで見ていた番組もテレビで見るようになりました。
ソファーはずいぶん後ろに移動。
でもこれなら、もっと年老いても、万一ベッドの生活になっても情報はクリアに得られそうです。
室内の電球も変えました。
介護施設では暖色が使われています。
暖かみはありますが、施設の入居者より若い院長にとっても暗く感じ、この明るさの下で本を読んだり書きものをする気にはなれません。
ムードよりも明るさが重要。
若い人とは感じ方が違い(白内障などで)より暗く感じるので、むしろより明るくした方が活動的になります。
(活動的を施設は求めていないのかもしれませんが)
LED仕様にしたこともあり、以前よりずっと明るくなりました。
少しムードのあった部屋も、明るくなったことで最初は戸惑いましたが、すぐ慣れました。
蛍光色ばかりでは味気ないですが、活動する場はメリハリをつけ明るくすると、読書も書き物もしたくなります。
明るくしたことで、汚れも気になるようになり、今年は毎日10分掃除を課すことにしました。
クリニックの通路階段も変えました。
階段は幅も広く問題ありませんが、人感式のライトは反応が悪くなっっていたので総入れ替え。
加えて、階段のステップには黄色い蛍光テープを貼ってもらいました。
緑内障で下方が見えにくい患者さんには、踏み外し防止でお勧めしていたのですが、実際に体験すると、階段のヘリがはっきり確認できるので上りも下りも安心できます。
スタッフは全員院長より年下なので、その恩恵はもっぱら院長だけかもしれませんが。
30代の頃には50代のライフスタイルの体験記やエッセイを読み、40代の頃には60代の…の自身としては、未来(老後)の生活を考える・想像することは、悲観よりむしろ楽しいことです。
年上の知人たちの活躍・行動を含むライフスタイルはまさにお手本。
今年も人生について、老後について学ぶこと多いだろうな~
昨年は多くの若い知人と縁が出来ました。
若い人の感性に触れることで、年下からも学ぶこと多し。
会いたいなぁと思われる人に。
話したいなぁと思われる人に。
『しない』のではなく『する』と決めよう。
老後へのグレーゾーンを行く院長。
未来(老後)を少しでも明るく!
今年もよろしくお願いします。
こちらもご覧ください