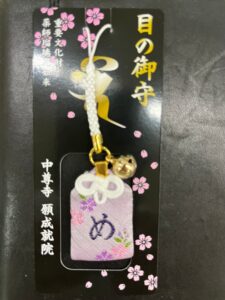2023.12.12 簡単に手に入るけど…
『コンタクトレンズが欲しい』
コンタクトレンズ(CL)希望の患者さんは毎日来院されます。
ただし、CL量販店やネット購入が容易に出来るようになったせいか、当院のような専門医のいる眼科で処方・定期検査を受ける患者さんは以前より少なくなっています(日本コンタクトレンズ学会調べ)。
一般眼科の併設CL店では、量販店やネットほど安くはありません。
ただし、一流メーカーオリジナルの定期購入お得プランはあります。
当院の強みは、院長が患者さんを把握、生活や訴えに応じてレンズの種類や度数を決定していること。
その時のヒアリングはとても重要です。
何を一番見たいか?
どんな仕事に対応?
どんな趣味に対応?などなど。
しっかり聞くことで患者さんとの距離も近くなります。
トライ&エラーもあり。
最終的に満足(もしくは妥協)のレンズを探します。
また、CL処方の可否だけでなく、『他に病気は、ねーが?(秋田弁)』を意識して他の病気の早期発見・早期治療を心がけていること。
さらに、CL以外のお悩み相談?にも速やかに対応するところ、だと思っています。
先日、患者さん(中学生)が、度が合わなくなったからソフトとソフトコンタクトレンズ(SCL)希望で来院。
装用してきたレンズの度数は、現在の近視の半分。
聞けば、2年前に量販店で処方された度数をそのままネットで購入し続けていたとのこと。
もちろん定期検査はなし。
そして充血がひどい。
本人も家族も『いつものことだから』
いやいや…
重度のアレルギー性結膜炎。
CLを中止して治療です。
眼鏡も持っていないので、すぐに作るように話しました。
CLは眼鏡と併用で。
眼科医の定期検査を必ず受けること(自覚と他覚は違います)。
CL店(みどりコンタクト)を併設する眼科医(院長)は、毎年、『コンタクトレンズ販売管理者継続的研修』を受けます。
CLは高度管理医療機器なのでそれに伴う法律の確認や、CLの合併症(権威ある眼科医の講義)など再度勉強します。
SCLの合併症は20~30代(最近は10代も)が最も多い。
1デイSCLでも、正しく使用しないと合併症が起こります(使用は1回限り)。
合併症の中でも、失明に至ることもあるのは、角膜炎。
緑膿菌とアカントアメーバが2大原因菌。
SCLは水道水は禁忌・こすり洗いも保存も専用液でしましょう。
こすり洗いが重要。
オールインワンタイプの洗浄液は便利ですが、消毒力では過酸化水素やポピヨンヨードが優れています。
レンズケースも意外に汚染されているので、自然乾燥を心がけ、SCLは1.5~3か月毎、HCLは半年から1年毎に新品に。
HCLは長期使用しない場合でも、週に1度は保存液を換えましょう。
長く当院でCL定期検査を継続される患者さんには、急にドカン!としたことは起こりません。
CL処方が目的ですが、いくらかは院長(の診察)目当てで来院されているなら嬉しいです(勝手な妄想)。
正しく使用すれば、生活の質を向上させる優れた高度管理医療機器。
でも…簡単に手に入る世の中。
正しい知識も価値も取り扱いも知らないまま手に入れられることは、一見ラッキーに見えます。
コスパもタイパもその時は良いかもしれません。
でも長い人生、ドカン!が起こり得ること・その代償も考えると、コスパもタイパも均(なら)されるのでは…と、オバサン院長は思います。
眼科医によるCL処方・定期検査を受けましょう!